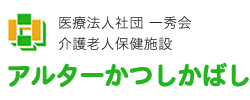「桃の節句」は七草、端午、七夕などと並ぶ五節句のひとつ。
本来は「上巳(じょうし、じょうみ)の節句」といい3月の最初の
巳の日を指していたのが、のちに3月3日に定まったそうです。
「桃の節句」と呼ばれるようになったのは旧暦の3月3日頃に
桃の花が咲くことや、桃は魔除けの効果を持つと信じられていた
事に由来。ひな祭りには子供に災いが降りかからないようにという
家族の願いや、人生の幸福が得られるようにという気持ちを込めて、
ひな人形を飾るようになりました。
ひな祭りに雛人形を飾るのは昔の人形(ひとがた)や流し雛の風習の
通り、お雛様に女の子の穢れを移して厄災を身代わりに引き受けて
もらうため、厄払いの意味があるので一夜飾りは避けるべきと
されています。遅くとも2月中旬くらいまでに飾るのが良いとされています。
節分で厄払いをした後に飾り始めると覚えておくと良いそうです。
日本の伝統文化を再認識し、魔除けと長寿の意味を持つ桃の花を見て、
桃の葉が入ったお風呂に入って邪気祓いを行ってみてはいかがですか?
介護主任 金野